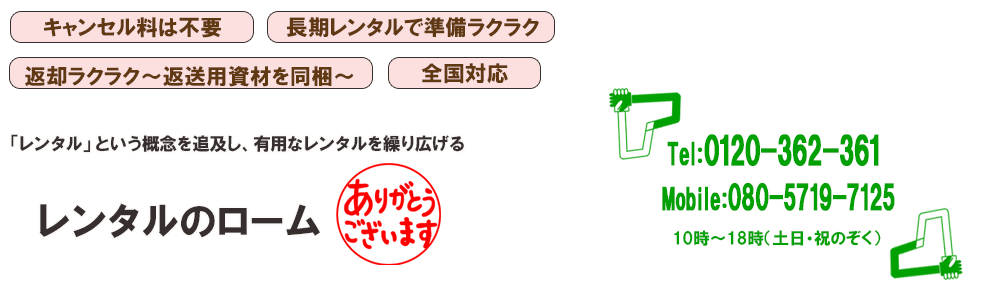美由さんはパチンと指を鳴らし、「お願いします!」と高らかに発声しました。すると、背後の席から私と同じくらいの年齢の女性が現れ、ゆっくりとこちらに歩いて来るではありませんか。そんな、まさか……。
にやりと笑って、パチンと指を鳴らした美由さん。
「お願いします!」と高らかに発生すると、出てきたのは私と同じくらいの年齢の女性でした。
前編はこちら
レンタルおばあちゃん
https://www.rentalism.jp/note/379/
・・・・・
「こんなこともあろうかと、私も呼んでおいたの。レンタルおばあちゃん。」
なんということでしょう。レンタルおばあちゃんが二人……。
しかも、相手のレンタルおばあちゃん、只者ではありません。目尻の皺の入り具合、腰の曲がり具合、身長、表情、仕草、その全てが絶妙で、その姿はまさに、みんなの理想のおばあちゃん。そして極めつけは髪型です。
豊かな白髪を頭のてっぺんでまん丸のお団子にまとめています。おばあちゃんをイラストで表現するときの定番の髪型ではありますが、現実、毛量が減りがちな高齢者にとってこの髪形は非常に難易度が高く、選ばれし者しか成し得ません。
「なんて強力なおばあちゃんなの……!」
思わず腰が引ける私。そんな私の手を握る沙希さん。
「おばあちゃん、お願い、負けないで……!」
そうだ、私は依頼人の笑顔のために全力を尽くすレンタルおばあちゃん。どんな状況でも、諦めるわけにはいきません。おばあちゃんらしさなら、私だって負けないわ。

「祐二さん、沙希さんは本当にあなたのことを愛してくれているのよ。そんな沙希さんの気持ちを裏切っていいわけがないわ。これでも食べて、落ち着いて考えてみて?」
私は巾着バッグの中からルマンドを祐二さんに差し出しました。そんな私を押し退けるように、お団子おばあちゃんが割り込んできます。
「祐二さん、あなたまだ若いんだから、過去の恋に囚われちゃだめよ。他に気になる人ができたならすっぱりお断りして、次に進まなきゃ。そうでしょう? さあ、これでもお食べなさい。」
お団子おばあちゃんは四輪の手押し車から寒天とグミの中間みたいな食感の砂糖がまぶしてあるアレを取り出し、祐二さんの手に握らせました。やるわね、でもまだまだ。
「みかんもあるの、剥いてあげる!白い筋は全部取ってあげるから!」
「そんなの私の方がきれいにできるわよ!皮はここに捨ててね。はい、チラシで作った四角い入れ物!」
「どこか怪我してるところはない? アロエあるわよ。」
「黄ばんじゃったシャツとかないかしら? どういう理屈かわからないやり方で真っ白にしてあげる。」
「ほらこれ、自分は飲まないのになぜか毎年作っている梅酒よ。」
「わらびの煮物があるの。食べてみて。」
お団子おばあちゃんのわらびの煮物、なんて鮮やかな色なのかしら。きっと重曹で色出ししているに違いない……。くっ、ここまでか……。

私が諦めかけたそのとき、ヒールの音がコツコツと軽快に近づいてくるのに気が付きました。
向こうから歩いてきたのは、白髪のロングヘアにサングラスをかけた女性。黒い革ジャンに細身のパンツ、ドクロのアクセサリーを身に纏ったその人は、たぶん私と年齢は同じくらいなのだけれど、背筋が伸びていて、堂々としていて、なんてロックでかっこいい……。
・・・・・
「おばあちゃん!」
祐二さんが満面の笑みで呼びかけます。
「え!?」
「俺の実のおばあちゃん。こんなこともあろうかと呼んでおいたんだ。本当ちょうどいいところに来てくれた!ねえ、おばあちゃん。俺、沙希ちゃんと美由ちゃん、どっちを選べばいいと思う?」
祐二さんがロックおばあちゃんにすがりつくようにして尋ねると、ロックおばあちゃんは「バカ言ってんじゃないよ!」と祐二さんの頭をバシッと叩きました。
「そんなことすら自分で決められないなんて、あんたは恋愛のレの字もわかっちゃいない。二股なんて100年早いよ。家に帰って根性叩き直してやる!さあ行くよ!」
祐二さんはロックおばあちゃんに首根っこを掴まれて帰っていきました。やっぱり、実のおばあちゃんには敵いません。そして何より、この年齢になっても自分らしさを貫き通すロックおばあちゃんの姿が私にはとても眩しかった。平凡なおばあちゃんであることしか取り柄のない自分が、なんだか恥ずかしくなりました。
「なんで私、あんな人のこと好きだったんだろう。」
「私も。」
沙希さんと美由さんも、どうやら祐二さんのあまりの情けなさに、さすがに愛想を尽かしたようです。二人して溜息をついたあと、私たちに「ありがとうございました」と頭を下げて、それぞれ帰っていきました。
さて、私とお団子おばあちゃんはどうしたかというと、なんと、そのままカフェに残って二時間近くお喋りしました。レンタルおばあちゃん同士、仕事の話で大盛り上がりしたのです。連絡先も交換しました。新しいお友達ができたのなんて、何十年ぶりかしら。
「祐二さんのおばあちゃん、かっこよかったわね。それに引き換え私は、なんてつまらない普通のおばあちゃんなんだろう。」
私がそう弱音を吐くと、お団子おばあちゃんは私の手を両手でぎゅっと包み込んで、「私だってそうよ。普通のおばあちゃん。ほら見て。」
お団子おばあちゃんが自分の頭に手をやって……なんと、お団子が取れた!大きなお団子は、かつらだったのです。
「私も普通すぎる自分が嫌で、こうして盛っちゃってたの、ウフフ。でも普通のおばあちゃんでいいのよね。むしろ、この仕事ではそれが喜ばれる。普通のおばあちゃんに、みんな会いたがっているんだもん。」
「そうか、そうよね。それでいいのよね。」
平凡なおばあちゃんの私にとって、やっぱりレンタルおばあちゃんは天職なのだと思います。同業者のお友達もできて、これからますます楽しくなりそうです。
<完>
===
編集後記:
おばあちゃんっ子。なんて平和で温暖で平原の中の一軒家の豊かな響きだろう。いっぽう、おじいちゃんっ子。なんて希少な響きだろう。
そう、この豊かさは幼少期の孫娘のほんのわずかな時間だけ享受できる、切ないものだ。
あのときは「おじいちゃん!」と高い声で呼ばれて楽しかったが、
今は「オ ジ イ チ ャ ン( ̄  ̄) 」という低く無機質な声で、彼女が作ったヒエラルキーが分かってしまう。
求められていないとは思わない。刹那的とは思わない。おばあちゃんが永遠なんだ。
涙を乾かそう。
業務用扇風機レンタル
https://www.roumu-p.com/fan/