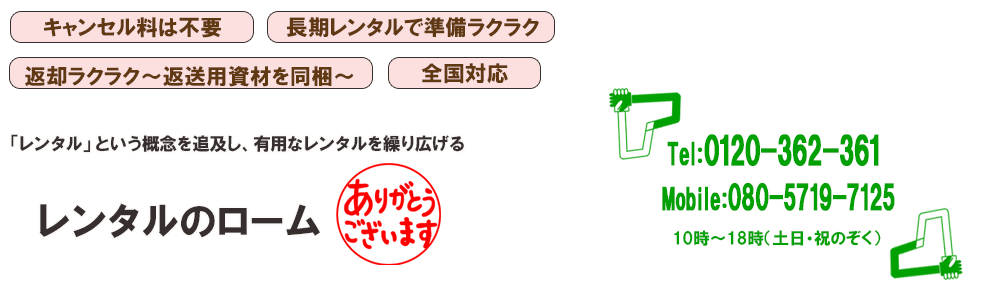今日、じいちゃんが死んだ。急に倒れて、そのままぽっくり逝ってしまった。僕とじいちゃんは二人暮らしで、お互いにとって唯一の家族だった。僕は今、酷く絶望している。たった一人の家族を失った、というのは勿論だが、何を隠そう、僕は引き籠りのニートなのである。
就職活動に失敗し、途方に暮れ、途方に暮れた勢いそのままに引き籠ってしまったのが三年前。それからというもの、ずっとじいちゃんの年金を当てに暮らしてきた。じいちゃんは何も言わず、毎日呑気に酒を飲んでいた。優しさというより、諦められていたのかもしれない。
これからの生活は絶望的である。三年間、ほとんど家から出ず、じいちゃん以外の人間とまともに会話していない。友達とも疎遠になってしまった。頼れる人が誰もいない。喫緊の問題として、葬儀とか届け出とか、何をどうすればいいのか皆目見当がつかない。何かしようにも金がない。通帳はどこだろう。財産とか、どれくらいあるのだろう。正直、しばらくこのまま暮らせるくらいの額があると助かる。
とりあえず引き出しを片っ端から漁ってみることにした。たんすの一番上の引き出しを開けてみると、開けた途端にじいちゃんの筆跡が飛び込んできた。
≪実へ。俺に何かあったら、この人に連絡すべし。≫
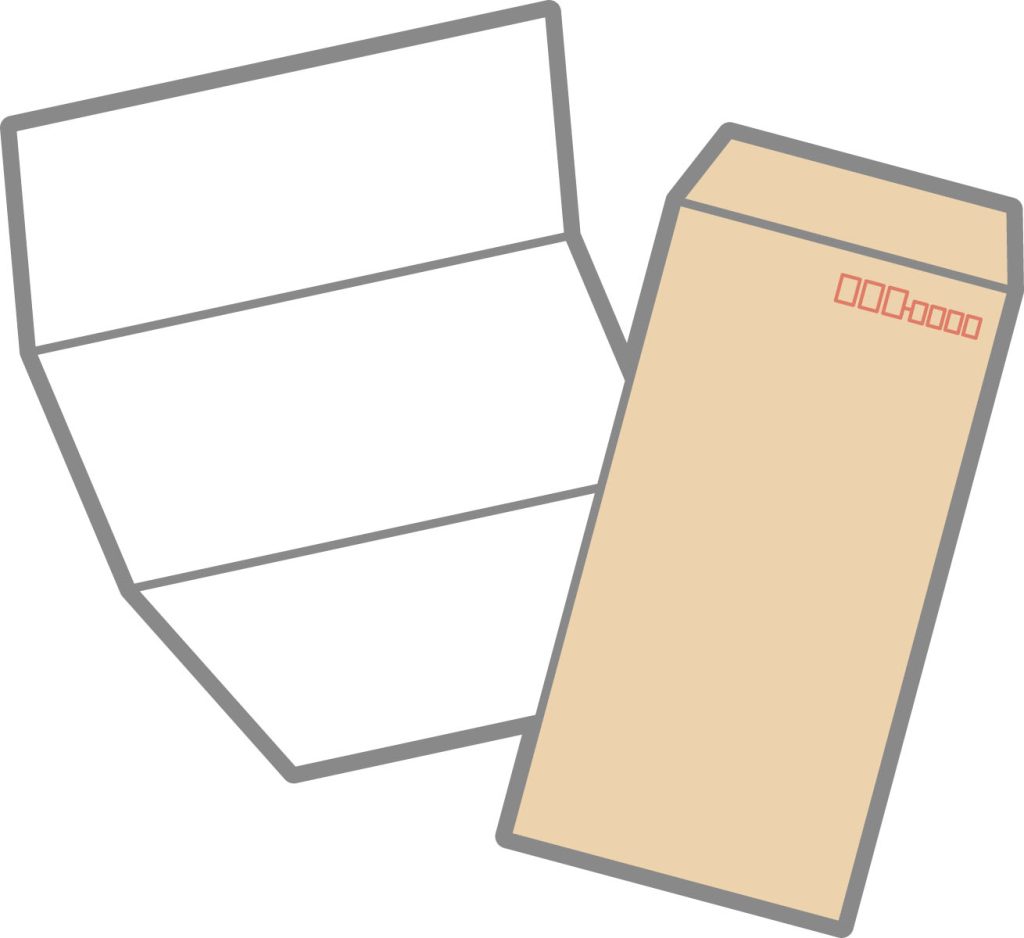
メモにはそう書いてあり、電話番号もあった。どういうことだろう。わからなかったが、藁にも縋る思いでその番号に電話をかけた。男の人が出た。
「ご安心ください。おじいさまから生前に承っております。」
事情を説明すると、その人は穏やかな口調でそう言った。どうやら葬儀社の人らしい。じいちゃんから自分が死んだあとのことを任されており、料金もすでに支払われているとのことだった。葬式はしなくていいと希望していたそうで、誰も呼ばず、火葬だけで見送ることになった。
「おじいさまには大変お世話になったんですよ。」
無事に火葬が終わったあと、その人は目を赤くしながら言った。そして、「これ、見てください」と、自分の髪を摘み上げ、僕に見せた。
「私、一年前まで物凄く禿げていたんです。正真正銘、禿げ上がっていたんです。もう諦めていたんですが、実さんのおじいさまとたまたま酒場で仲良くなって、この発毛剤を使えとか、これを食べろとか、いろいろ教えていただいたんです。それを試してみたら、ほらこんなに! 感謝してもしきれません。」
「はあ、そうなんですか。」
確かにじいちゃんは歳の割に髪が多い方だったが、自ら増毛メソッドを確立していたとは知らなかった。引き籠りニートの僕が言えたことではないが、じいちゃんも大概ちゃらんぽらんな男だったので、あの酔って前後不覚になることがライフワークみたいな爺がこんなに人から感謝されているなんて、俄かには信じがたいことである。
「何か困ったことがあったら、いつでも連絡くださいね。髪が気になり始めたら、おじいさまから聞いたことをお教えしますので、こっそり聞きに来てください。おじいさま曰く、実さんも“もうすぐ”らしいですよ。遺伝的に。」
その人は小声でそう言ったあと、ポケットから一通の手紙を差し出した。
「こちら、おじいさまからお渡しするように言われていたものです。」
僕はそれを受け取り、じいちゃんの骨壺と共に火葬場をあとにした。
なんだかフワフワした気分だった。じいちゃんが死んだからなのか、久しぶりにじいちゃん以外の人間とまともに会話したからなのか、初めて他人からじいちゃんの話を聞いたからなのか、予期せぬタイミングで自分が若くして禿げる可能性を示唆されたからなのか。
公園のベンチに座って、さっき渡された手紙を読んでみることにした。じいちゃんの遺書に違いない。きっと通帳の場所とか、財産のことも書いてあるだろう。
≪実へ。2丁目のパン屋に行って、ガーリックトーストと焼酎を注文すべし。≫

意味が分からず何度も読み返してみたが、どうやら遺書ではないらしい。パン屋に焼酎は売ってないだろう。酔って書いたのか? 隣に置いてある骨壺を睨み付けてみても、当然ながら返事はない。
2丁目のパン屋は知っている。開店の花が飾られているのを見かけて、気になっていた。ただ、そのあとすぐ引き籠ったので入ったことはない。
手紙の意図は不明だが、考えていても仕方がないので、とりあえずパン屋の前まで歩いた。小さい店だが、客が頻繁に出入りして賑わっているようだ。パンが焼けるいい匂いもする。その匂いに引っ張られるようにして、僕はええいと店の中に入った。レジには女性の店員が一人立っていた。僕は俯き加減でそこに突き進む。
「すみません、あ、ええと、ガーリックトーストと、しょ、焼酎を……。」
長年引き籠っていてコミュニケーションに難のある人間に、こんな酒いどれの妄言みたいなふざけた注文をさせるなんて、もしかすると、じいちゃんは働きもせず引き籠り続けていた僕を内心恨んでいたのだろうか。そうでないとこの辱めの説明がつかない。
「ああ~! 少々お待ちくださいね。」
えっ嘘、焼酎あるの?
信じられない気持ちで待っていると、女性が裏から戻ってきて、渡されたのは、手紙。また手紙である。
「実くんもガーリックトースト好き?」
「え、はい、好きですけど……。」
「実くんのおじいちゃん、うちのガーリックトースト好きでね、しょっちゅう買ってくれてたの。で、これ本当に感謝してるんだけど、ある時、おじいちゃんが『ここのガーリックトーストは焼酎に合うぞ。他の客にも勧めた方がいい』って。それがきっかけで、お店のSNSでパンとお酒のマリアージュを紹介してみたら、想像以上にたくさん読んでもらえてね。お客さんすごく増えたんだよ!」
女性は大きな目を更に大きく見開きながら話した。そうか、時々ニンニクのいい香りが二階の僕の部屋まで漂ってくることがあったが、じいちゃんはここのガーリックトーストで一杯やっていたのか。
「実くんも買いにきてね。ガーリックトースト以外にもいろいろあるからね。」
女性は僕が店を出て通りの角を曲がるまでずっと手を振っていた。僕にだけじゃなく、僕の抱いている骨壺に向けて振っているようにも見えた。
さて、もらった手紙を開けてみる。
≪実へ。スナック美里に行って、珈琲焼酎と大福を注文し、カラオケでB’zを歌うべし。≫

僕は思わず頭を抱えた。“すべし”のハードルが高くなっている。スナック美里はうちの近所に昔からある店で、看板はよく知っているがやっぱり入ったことはない。
しかし、ここにきて思い出したことがある。僕が小さい頃、じいちゃんは毎年僕の誕生日に家の中で宝探しゲームを開催した。指定の場所に行くと次の場所のヒントが書いてあり、冷凍庫、こたつの裏、枕カバーの中、図鑑のトンボのページ、桜模様のお菓子箱、などと辿っていくと、最後に誕生日プレゼントに行き着く。
つまり、手紙を辿っていったこの先には恐らくプレゼントがあるに違いない。今の僕にとってのプレゼント、それは通帳、もしくは何かしらの財産。となれば、もうやるしかない。
僕はスナック美里のドアを開けた。カランカランと音がして、ママらしき人が「いらっしゃい」と声をかけてきた。思ったより若いママだ。三十代後半くらいだろうか。
「すみません、えっと、珈琲焼酎と、大福をください。」
「はあい、待ってね。」
「あとカラオケしたいんですけど。」
「はあい、デンモク。」
僕はデンモクを操作して、『さまよえる蒼い弾丸』を入れた。イントロが流れると同時に、「はあい、マイク。」と手元にマイクが出てきた。
歌詞を目で追いながら、必死に腹から声を出す。この爽快感、久しぶりだ。大学生の頃は同期のみんなでよくカラオケに行った。僕が大学に行かなくなってからも遊びの誘いはあったが、就職が決まっている友人たちと会うのが嫌で断るうちに、誰からも連絡が来なくなった。
「実くん、歌上手いじゃん! 若い頃の稲葉さんみたい!」
歌い終わると、ママが拍手しながら歓声を上げた。テーブルには珈琲焼酎と大福が用意されている。
「実くんのおじいちゃんも歌上手だったよ。私がB’zのファンだって言ったら、家で練習してきてくれたの。毎回のように違う曲。ここの客層からしてB’z歌ってくれる人っていなかったから、私、本当にそれが嬉しくてね。」
思い出した。そういえば夜中トイレに行こうとしたら、居間にいるじいちゃんがB’zを口ずさんでいて、何でB’zだよ、と思ったことが数回あった。あれは、この店で歌うための練習だったのだ。
あまり酒は得意でないのだが、歌ったら喉が渇いたので珈琲焼酎をぐびっといった。大福もほとんど一口で食べた。「おいしいですね、この大福。」と言うと、ママは「おじいちゃんもそれ大好きだった!」と、骨壺をちらっと見て笑った。
「実くん、またB’z聴かせてね。いつでも遊びに来てくれていいから。それとこれ、おじいちゃんから預かってた手紙。」
ママから手紙を受け取り、僕は店を後にした。珈琲焼酎が効いている。ぼーっとする頭で手紙を開く。
≪実へ。桜のお菓子箱を開けるべし。≫

後編に続く↓
祖父が遺してくれたもの=一歩踏み出す勇気!
https://www.rentalism.jp/note/422/
レンタルのローム
https://www.roumu-p.com/
電動ハンマーのレンタルはこちら
https://www.roumu-p.com/6/