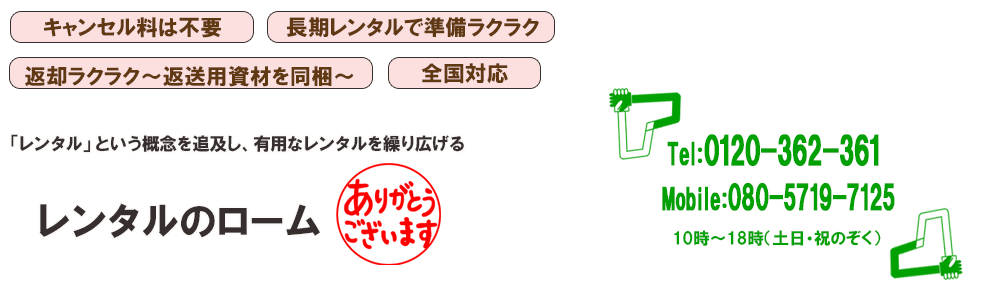「また引っ越したんだって?」
林は僕が電話に出るなり、食い気味にそう聞いてきた。
「今度はどの辺?」
「T駅の近くだよ。前の家から徒歩5分のとこ。」
「はあ? またそこ? もう三回目だろ!」
林の呆れ返った叫び声が鼓膜にキンキンきて、僕は思わずスマホを耳から遠ざけた。確かに僕は、この2年間で3回も引っ越しをしている。それも、同じエリアの中で。
「お前くらいだぞ、今も大学の近くに住んでるのは。しかも意味なくウロチョロ引っ越しやがって、ヤドカリかよ。」
「いや、交通の便がいいんだよ。会社にも一本で行けるし。あと前の家は夏になると蝉の死骸が……。」
「あ、そうだ!」
僕が理由を並べているのを遮り、林がまた大声を出した。
「お前に教えなきゃいけないことがあったんだ。先週、お前が来なかった同期の飲み会あったろ? そのとき女子からチラッと聞いたんだけど、あみちゃんT駅の近くに引っ越したらしいぞ。」
「え?」
「一瞬思ったんだよ。もしやお前とより戻したのかって。でもさ、もしそうだったら有頂天のお前から報告がくるはずじゃん。だから絶対違うよなって。でも知らせとかないと、ばったり会ったりしたらお前の心臓が爆発するかもしれないからさ、てか、もしばったり会えたらそれきっかけで復活したりして? なんてことはないか、いや可能性ゼロじゃないかも。どうなの? ねえ、聞いてる?」
あみちゃん。その名前が出た瞬間、林のバカでかい喋り声はボリュームが勝手にギューっと絞られて、僕の耳にほとんど届かなくなった。

あみちゃんがよく遊びにきていた大学時代の部屋は、別れたあとすぐに引っ越した。そのあと、日当たりがどうとか、壁の模様がどうとか自分の中でいろいろ理由をつけて、更に2回引っ越した。あみちゃんとの思い出を振り切りたくて引っ越すのだが、結局いつも同じ、あみちゃんと過ごしたこの街を選んでしまう。自分でも意味不明だ。しかも、別れたときに思い出の品を片っ端から詰め込んで封印したダンボールも一緒に引き連れて。捨てよう捨てようと思いつつ、押し入れから押し入れへとただ移し替えている。ダンボールを捨てればいい、この街から出ればいい、それはわかっているのだが、そうしてしまうと、なんだか忘れちゃいけないことを忘れてしまいそうな気がして、できなかった。
久しぶりにあみちゃんの名前を聞いたら、無性にあの映画が観たくなった。彼女いない暦=年齢の暗いオタク青年が電車で助けた女性に恋をして成長する話。
「高尾くんは“自転車男”だよね。」
付き合い出してすぐの頃、その映画を観てあみちゃんは言った。
僕があみちゃんと初めて話したのは、駅前の自転車置き場だった。大学の同期であるあみちゃんのことは知っていたけど、あみちゃんは明るくていつもみんなに囲まれているような人で、一方、僕はいつも一人もしくは同じ高校だった林しか話す相手がいないような人間だったから、それまで話す機会がなかった。
その夜、僕はバイトが終わって家に帰る途中、駅前の自転車置き場で誰かが言い争っているのを見かけた。
「やめてください! それ私の自転車ですから!」
普段なら目を合わせないように素通りするところだが、それがあみちゃんだと気づいて、思わず自転車のペダルを止めた。
言い争っている相手は中年の男だった。「俺のチャリだっつってんだろ!」と怒声を上げ、明らかに酔っ払っている様子だった。
「ちょっと、壊れちゃうじゃないですか!」
あみちゃんの必死の訴えを無視して、男は自転車の鍵を力ずくでガチャガチャやっている。
「あ、あの! こっちにも赤い自転車ありますけど、これじゃないですか?」
僕にしては頑張ったと思う。酔っ払いは振り返って「ああ?」とすごんだあと、こちらに近づいて僕の横にある自転車を確認した。そして、「はあ〜」と謎のため息を吐き、僕を突き飛ばして、ふらつきながらその自転車に乗って去っていた。
あの映画では電車で助けた女性からお礼にエルメスのティーカップが送られてくるが、あみちゃんはジョリーパスタでピザを奢ってくれた。僕はあみちゃんと付き合って変わったと思う。見た目にも気を遣うようになったし、前よりは積極的に人と話せるようになった。
登録しているサブスクを探してみるが、あの映画は配信されていなかった。やっぱり、と思った。実はあみちゃんと一緒に観たときも、動画配信サービスを片っ端から探したがどこにもなくて、レンタルショップをいくつか巡ってやっと見つけたのだ。街のはずれにある寂れた小さなレンタルショップだった。見つけた瞬間、二人で抱き合って大喜びした。その程度のことが、あみちゃんといると楽しくて仕方がなかった。

後編はこちら↓
忘れちゃいけないこと
https://www.rentalism.jp/note/614/
レンタルのロームはこちら
https://www.roumu-p.com/