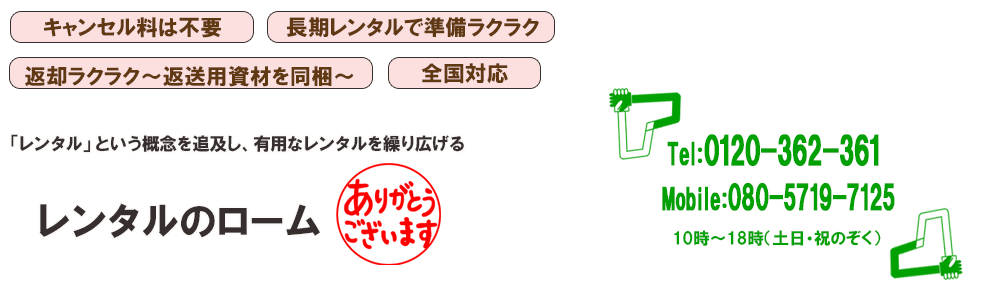岡山市、冬の季節は空気が乾燥し、人々は自然と心の渇きを感じ始める。そんな中、市の一角にある小さなレンタルショップ「モイスチャーハーバー」が、人々に必要な潤いを提供する場所として静かにその役割を果たしていた。店主の佐知子は、加湿器をただの家電製品とは考えず、冬の乾燥した日々に温かさと潤いをもたらす魔法の道具と信じている。
主人公、陽介は岡山生まれの大学生で、冬休みに「モイスチャーハーバー」でアルバイトを始めることになる。彼は当初、加湿器のレンタルなど地味な仕事に興味を持てずにいたが、佐知子との出会い、そして様々な顧客との交流を通じて、加湿器が人々の生活にもたらす小さな幸せに気付き始める。
「加湿くかい?いや、加湿かれるのかい?」この疑問を投げかけるように、陽介は一人の老婦人、美恵子と出会う。彼女は冬の乾燥で息苦しさを感じており、息子からの勧めで加湿器のレンタルを求めに来た。陽介が美恵子の家に加湿器を届けると、彼女の部屋はすぐに温かく潤いあふれる空間へと変わる。美恵子は、加湿器から立ち上る蒸気を見つめながら、遠い昔、夫と過ごした岡山の冬の思い出を語り始める。
この出会いは、陽介にとってターニングポイントとなる。彼は美恵子の話から、加湿器が単に空気を潤すだけでなく、心を潤し、過去の記憶や人々の間の絆をも呼び覚ます力を持っていることを学ぶ。そして、岡山の冬が持つ、厳しい寒さの中にある温かな人間関係の美しさに気付く。
物語は陽介が「モイスチャーハーバー」での経験を通じて、人との繋がり、思いやり、そして心の潤いの重要性を理解していく過程を描く。彼は、加湿器のレンタルを通じて、岡山の人々に小さな幸せと潤いを届けることの価値を深く認識するようになる。
最終的に、陽介は、冬の終わりに「モイスチャーハーバー」で開催される小さなイベントで、加湿器とともに過ごした冬の思い出や感謝の言葉を顧客たちと共有する。岡山の冬の寒さを乗り越えた人々が集い、共に温もりと潤いを分かち合うこの場所は、陽介にとっても、心のありかとなる。